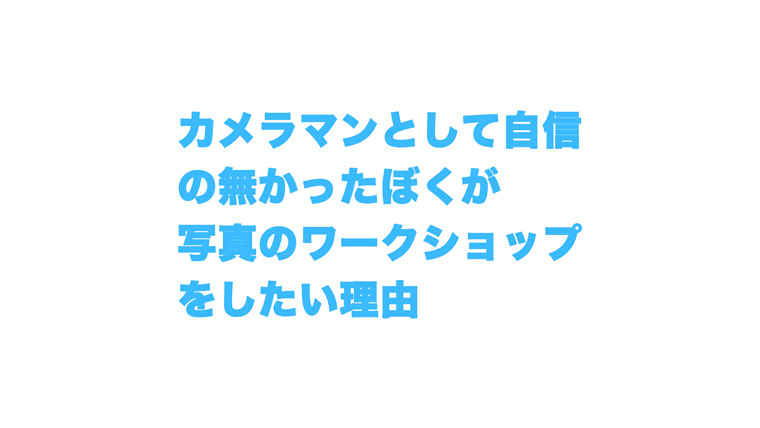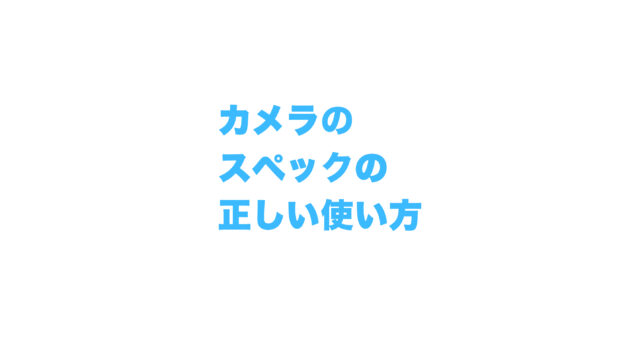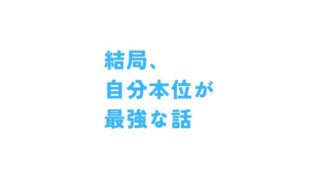ただ写真を撮ることが好きなだけだったのに、ぼくはボタンを掛け違えた。
上手い写真?
センスある写真?
そんなのどーでもいい!!
そう思いながらも「写真の上手さ」や「センス」を一番気にしていたのは紛れも無く、
ぼくだ。
もっと言うと、「そんなのどーでもいい!!」なんて真っ向からぶつかる強さもなかった。
なんとなく雰囲気に流されて、
「写真は上手い方がいいんだろうな…」
「センスある方がいいんだろうな…」
「けどぼくはセンスない…」
「そもそも写真の学校を出ているわけでもないし…」
なんて言い訳を並べて、縮こまって、劣等感にまみれて、自分の表現に蓋をした。
自分の表現を自分が一番否定していた。
なぜそんな風になってしまったのか。
ワケを話そうと思う。
ぼくが写真(カメラ)に本格的に出会ったのは、大学3年生。21歳の時。
大学3年生になると”ゼミ”に入り、そこで学んだものの”卒業論文”を提出して初めて卒業することができる。
ただ、ぼくは文章を書くことが大嫌いだった。
今でこそこんなブログを書いているけど、当時は本当に大嫌いだった。
でもそんな”卒論”を免れる唯一の方法があった。
それは”卒論”じゃなく”卒業制作”をすれば卒業の切符を手に入れられるゼミに入ること。
それが写真を扱うゼミだった。
ぼくはそのゼミに即決。
ただ、そこに入るにはこんな条件があった。
・実際に写真を撮るのでカメラを用意してください
・本格的な一眼レフカメラはいらないけど、コンパクトデジタルカメラくらいは用意してください
当時はガラケーの時代。携帯についているカメラでは少々役不足だった。
元々写真を撮ることが好きだったぼくにとってその条件はゆるいもの。
せっかくならとデジタル一眼レフカメラを買った。
そんな感じでぼくは「写真(カメラ)」と本格的に出会った。
ここでちょっと補足。
本格的に出会う前、それは高校生の時に遡る。
当時はガラケーにカメラ機能が付き始めた頃で、それは画期的だった。
中学生の間は携帯電話を持っていなかったけど、高校生になり持たせてもらえることになった。
これがぼくとカメラとのいっちばん最初の出会い。
携帯電話そのものも嬉しかったけど、何より「写真を撮ること」が楽しくて、それはぼくの日常になった。
通学途中の風景や自然をよく撮った。
おそらくこれが原体験。
そんな感じで高校生の頃から写真を撮ることは好きで、大学生になると一眼レフを買ってさらに本格的に撮影の世界にのめり込んでいくことになった。
ただ、撮影の基本スタンスはずっと変わらなかったように思う。
というか「撮影の基本スタンス」なんて仰々しいものも無く、“ただ感じたままに”撮っていた。
「わぁ〜綺麗だなぁ」と思ったらパシャリ
「うわっ、なにあれ、すごい!」と思ったらパシャリ
「なにこれwおもしろいww」と思ったらパシャリ
そんな風にして、基本的に心が動いたとき自然とそれは「撮影」という行為に流れていった。
さて、
ここまでの話をまとめると、これはつまりどういうことか。
ぼくにとって写真は、自分の価値観を写し出したもの。
価値観そのもの。
なんですよね。
「写真」って、「真実を写す」って書きますよね。
だから写真って「被写体の真実そのままを捉えて写すもの」と思いがち。
物質的な意味でね。
けど実はそうじゃなくて、写真という言葉の本当の意味は「真(まごころ)を写す」ってことだと思うんですよね。
真(まごころ)っていうのは「噓偽りや混じり気の無いもの」ということ。まさに自分の「本当の心」のことですよね。
つまり写真というのは、自分が心で価値を感じたもの、自分の価値観を写し出したもの。
今はここまで言語化できていますが、ただ楽しく写真を撮っていた高校大学時代はそんなこと深く考えずに撮っていました。
でもだからこそ、混じり気なくただ感じたままに、ありのままを撮れていたんですよね。
そして物語は続きます。
大学で写真と本格的に出会ってからしばらくして、ぼくにも就職活動の時期がやってきた。
周りも就活する中、ぼくはどこか違和感を覚えていた。
就職説明会で並ぶ企業名を見ても、全く魅力的に見えない。
それらの会社を悪く言いたいんじゃない。むしろほとんどが社会に必要な素晴らしい企業だと思う。
けどそういう会社に入って働くっていうのが全然しっくりこなかった。
生きていくために、お金を得るためにとりあえず就職する感…。
もっと自分はこう…自分の好きなことをして生きたい!
そういう想いが強かった。
けど「就職活動」という枠組みからハミ出るほどの勇気がなかったぼくは、とりあえず興味があった舞台照明関係の企業をいくつか受けることにした。
ただ、ほどなくしてそれらの企業は全て不採用。
さぁ、いよいよ追い詰められた。
どうしよう…
就職活動しないといけないけど、受けたい企業が本当にない…
というか自分が何をしたいのかがわからない…
そんな浮遊感を持ちながら何かヒントはないかと本屋に行くことにした。
ぶらぶらと見て周るも特にピンと来るものもなくどこか上の空。
最後に写真集のコーナーへ。
端からざーっと背表紙を見ていたとき、ある写真集が目に留まった。
本全体が真っ青な写真集。
青が好きなぼくは思わず手に取った。
そして帯を見ると「あなたは今、好きなことしていますか?」の文字。
完全に惹き込まれてその写真集を開くと、美しい青色の写真たちと共に「独学でカメラマンになった著者の経験談、そして夢に向かって一歩を踏み出せずにいる読者へのメッセージ」が書かれていた。
気がつくと立ち読みで全ページを読破。そのままレジに直行してその写真集を購入した。
立ち読みをしている間にぼくは決心していた。
「カメラマンになる」
と。
けどどうやってなればいいのかさっぱりわからない。
ありがたいことに、この著者がカメラマンのなり方を教えてくれるワークショップを開いているということだったので、ぼくは予約し大阪から東京まで会いに行くことに。
ワークショップに参加するにあたってぼくは、それまでに撮った写真の中から特にお気に入りの写真たちを大学のパソコンルームで印刷し持っていくことにした。
そしてワークショップ当日。
緊張しながら部屋の扉をノックした。
扉が開いて著者が「よくきたね」と出迎えてくれた。
少し緊張が緩んだのを感じながら椅子に座り、さっそくぼくの写真を見てもらう流れに。
カバンからファイルを取り出して渡す。
著者がざーっと写真を見て「この写真はなぜ撮ったの?」と聞いてきた。
ぼくは「んーそうですね…なんかいいなと感じて撮りました!」
著者は「なるほど」と言って再び写真たちに目を落とす。
そしてとある鹿の写真を見て「これはいいね」と言ってくれた。
すごく嬉しかったのを覚えている。
少し浮かれたぼくを察したのか、
「素人でも偶然こういういい写真を撮れることはある。いい写真と言っても比較的いい写真ね。ここにある他のと比べるといいってことね。」
と釘を刺された笑
そしてまたざーっと見て総評として、
「ただ撮ってるだけだね」
「写真が好きなんだろうなーっていうのは分かるけど、それだけ」
「あと他の人はもっとちゃんと一枚一枚を綺麗に写真用紙にプリントして一枚一枚を丁寧にファイリングしてくるよ」
「こんなただのA4用紙に何枚も写真を並べて印刷して持ってきたのは君くらい」
と言われた。
この場では素直にそれらの言葉を愛の鞭として受け取っていたつもりだった。
けど、やっぱりどこか胸がズキンと痛むというか、この後約15年にわたって「ただ撮ってるだけ」と言われた記憶だけが強烈に残ることになる。
そしてその記憶は「写真を否定された」という認識へと形を変える。
このワークショップの後、著者のアドバイス通り写真スタジオに就職した。
アシスタントとしてカメラマンを目指す日々。
そんな中、日常的に「いいな」と思った瞬間を撮ってFacebookなどのSNSにアップはしていたけど、周りの目をすごく気にしていた。
「いい写真」と言われたい。
特に、写真業界にいる人からの「評価」が気になった。
写真スタジオで知り合う広告系のカメラマンやディレクター、スタイリストさん、ヘアメイクさんなどなど、業界の人ともSNSで繋がりぼくの写真をそういう人たちにも見られることが多くなった。
そういう人たちから「いいね」が付かないとすごく気になった。
「あれ?いいね付いてない。やっぱりぼくの写真はダメなんだ。センスないんだ。業界で通用しないんだ。」
そんな風に思った。
そして「どうせ業界の人たちはぼくの写真をバカにしているんだ」と思うようになった。
あとは、スタジオの同期は写真学校出身で、ぼくは普通の四大出身。そんな部分に劣等感を感じたりもした。
後輩ができて、後輩の方が自分よりもカメラマンとしてバリバリ活動している姿を見て劣等感を感じたりもした。
さて、
ここまでの経験でぼくにはこういう思い込みが生まれていました。
・「ただ感動して撮る」だけじゃダメなんだ
・「いい写真」と言われるような「写真の上手さ」や「センス」が無いとダメなんだ
そして写真表現を心の底から楽しむことができなくなりました。
でもこれらは本当に思い込みでしかなかったんですよね。
今、改めてこれらの経験を思い返して感じるのは、
・ぼくが感覚的だった
・評価されるのが窮屈だった
ということ。
まず『ぼくが感覚的だった』ということについて。
ぼくは写真を撮るとき「空間」を撮りたいんですよね。
空間というか、「空気感」みたいなもの。
その「モノ」が持つ空気感。
この世のあらゆるモノが、それぞれに空気感を持っているように感じるんですよね。
森羅万象、全てのモノに神は宿るみたいな。八百万の神的な。
朝焼けの広い空にも、道にできた水たまりにも、ペン立てのボールペンにも空気感はある。
その中でビビッときた空気感を持つ「それ」を撮りたいんですよ。
で、「モノ」によって空気感の質が違うというか…
朝焼けとかって空気感が豪快だから意識してなくても目に入った瞬間「うわっすごい!」って心が動く。
ペン立てのボールペンにももちろん空気感はあるけど、繊細だから意識して感じにいかないといけなかったりする。
でもどちらが良い悪いじゃないんですよね。
ほんと、みんな違ってみんないい。
そんな風に感覚的に撮っていたぼくが聞かれたわけです。「この写真はなぜ撮ったの?」と。
これは、撮影に入る前のいわば根本的な問いだと思うんですよね。
ここに関してぼくは「空気感にビビッときたから」としか言いようがなかった。
だから急に質問されても曖昧にしか答えられなかったんだと思います。
ただ、ここの言語化って「カメラマン」として仕事をする上で超重要なんですよね。
ぼくも一応カメラマンの端くれとして7年ほど広告系の写真業界にいたので今は分かります。
カメラマンはディレクターやクライアントさんの意図を汲み取って、それを写真に落とし込む。
そして時には「なぜそういう風に撮ったか」を説明しないといけない。
「広告」は「広く知らせる」ための役割があるので、ターゲットに訴求できるような写真を論理的に組み立てる必要がある。
・訴求ポイントはどこなのか?
・そのための構図は?
・アングルは?
・露出は?
・不要なものは写ってない?
などなど。
中でも「訴求ポイントはどこなのか?」が重要で、これは言い換えると「一番魅力的なポイントはどこ?」ということ。
著者の「なぜ撮ったのか?」という問いは「何を魅力に感じて撮ったのか?」とも言え、ここに通ずるんですよね。
カメラマンにとって重要なことだから著者は質問をしたんだと思います。
「カメラマンとして求められる写真」にフォーカスした話をしていたんですよね。
「カメラマンへの道」というワークショップだったので当然です。
当時はここまで整理できていなかったので、自分の価値観のままに撮った写真を「ただ撮ってるだけ」と言われて否定されたと感じてしまいました。
そうじゃなく「ぼくの写真との向き合い方」と「カメラマンとして求められる写真」が違っていただけなんですよね。
ここを区別できずにぼくが突っ込んで行ってしまって起きた事故だった。だから著者を責めるつもりは一切ない。
むしろ、これは想像ですが「カメラマンになるならない関係なく”写真を撮る人”として成長してほしい。」そんな想いが著者にあったんじゃないでしょうか。
そして『評価されるのが窮屈だった』ということについて。
先述した通りぼくの中では、
「いい写真」と言われるような「写真の上手さ」や「センス」が無いとダメなんだ。
という思い込みがありました。
カメラマンとしてならある程度は「上手さ」などの指標は必要だとは思いますが、あまりにも囚われすぎていた。
その結果「写真が上手いかどうか?」という周りからの「評価」にがんじがらめになりました。
カメラマンとして更に成長するため、「評価」を受ける前提で撮った写真もありました。
それでも「評価」が怖かった。
とにかく他人からの目線が怖かった。
それなのにぼくも他人の写真を「評価」してしまったこともあります。
カメラマンとしてなんとかやって行きたくて、「その世界の人として」評価の目は持っておきたい。そんな想いからだったんだと思います。
プライベートにおいても「評価」は感じた。
ただ感動して撮っただけなのに「さすがカメラマン」と言われたり、記念写真を撮るときなんかに「ここはやっぱりカメラマンのUGお願い!」と言われたり…
友達は褒め言葉として言ってくれていたんだろうけど、とてもじゃないけどその「上手さにフォーカスした言葉」を受け入れることができなかった。
仕事でもプライベートでも、
「評価」をされることはすごく窮屈で、怖くて、
楽しくなかった。
そんな感じだったのでカメラマンとしての自分に自信が持てるはずもなく、
しんどくなって写真業界はやめました。
ここまでを振り返って今思うのは、
写真ってもっと自由でよくない?
ということ。
先述のプロセス「訴求ポイントは〜?」とか「構図は〜?」とかが満たされていない写真は、まだまだ伸び代があるかもしれない。改善の余地があるかもしれない。
むしろ論理的に組み立てて撮るというプロセスはカメラマンを「目指していなくても」とても重要だとすら思います。
・一番惹かれるポイント(訴求ポイント)はどこなのか?
・そのための構図は?
・アングルは?
・露出は?
・不要なものは写ってない?
などなど。
これら一つ一つに向き合い写真を洗練することで、より表現が濃縮され自分が感じたものを感じたままに伝えることができるようになると思うから。
でも、
プロセスを満たそうと意識しすぎると窮屈になってくるんですよね。
だから「なんかビビッときたから」で撮って、それを別の人が見て「私はこの写真のこの部分が好きだな」とか言って。
各々が自由にその「モノ」の空気感を感じていく、みんなでその作品を愛し育てていく、それだけでもいいんじゃないかと感じます。
もちろん、プロセスを満たした写真があってもいいと思います。
それも自由です。
そういう「意図」を聴くのも視野が広がって面白いですしね。
ただ、プロセスを満たすことが絶対的な正義ではない。
もっと曖昧な表現があってもいい。
ぼくはこういう考えを持っているので、「プロセスを満たすことが求められる」カメラマンの世界が窮屈だったんですよね。
「なんかビビッときたから」だけで撮ってもいい、「色々考えて」撮ってもいい、そうやって撮った写真について対話し、作品を愛し愛される。
それでよかったんだ。
そう気づきました。
こうやってぼくは周りからの「評価」に耐えられなかった。
もしかしたらぼくの思い過ごしだった場面もあるかもしれない。
それでも窮屈だった。
写真はぼくにとって価値観そのもの。
その写真を評価されるのは自分の存在を評価されるのと同義なのでそりゃ怖いですよね。
ていうか存在は評価するものじゃないと思うんです。
そのまま、ありのままで最高なんですよ。
だからぼくは伝えたい。
目をキラキラさせている人の無防備な感動に、
ぼくは寄り添って共感したい。
過去のぼく自身が欲しかった「体温を感じられるワークショップ」がしたい。
写真が大好きな人と、撮った写真についての「キャッチボール」がしたい。
写真を「評価」するのではなく、「寄り添い対話する」場を作りたい。
その場で「なぜこの写真を撮ろうと思ったの?」という質問があってもいいと思うんです。
けどそれは「評価」する前提じゃなく、対等な立場として「対話」するための質問。
撮影段階では「ビビッときたから撮った」だけでもいいと思うんです。対話する中で気づける事もあると思うから。
そうしているうちに撮影者の価値観を発掘できるかもしれない。
そしたらより一層その写真が好きになる。
上手い下手の議論じゃなく、
写真を通して他者との繋がりが深まる。自己理解が深まる。
そんな場を作れたらなって思います。
最近絵画に興味が出てきて、とある美術系YouTubeチャンネルを見漁ってるんです。
それまで絵画って見ても「ふ〜ん」としか思なかったのが、解説を聞くと作者の暮らしや状況、気持ちなんかが見えてきて、そうするとその絵の見え方が変わるんですよね。
深みが増すというか愛着が湧くというか、すごく尊いものに見えるんですよね。
絵画において「印象派」というものがあります。
まさに「その時感じた印象をあるがままに描くスタイル」
この印象派の代表的な画家にクロード・モネがいます。
彼が残した言葉、
「人は私の作品について議論し、まるで理解する必要があるかのように理解したふりをする。私の作品はただ愛するだけでよいのに。」
これはまさに「評価」でなく、ただ感じ愛してくれと言っているのだと思います。
ぼくたちが撮る写真も同じだと思うんです。
別に評価して欲しいわけじゃない。
そこには撮影者の気持ちがある。想いがある。価値観がある。
それを感じ愛したい、愛して欲しい。
だからぼくは、一緒に共感したり、価値観を見つけたりできる場を作りたいと心から思っています。
掛け違えていたボタンにようやく気づけた。
写真を撮ることが嫌いになりかけたけど、やっぱり大好きです。
ということで、オンラインでワークショップをやってます。しばらく無料です。